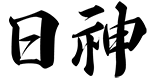熱田の大神様から熱田神宮の資料をいただきましたので、その一部を皆様にもシェアしたいと思います。
熱田神宮宮庁発行、熱田神宮昭和造営誌、非売品。御社の設計図から昭和の時代に行われた遷宮はじめ、昭和史が全て書かれている561ページにわたる資料です。
幼い頃に熱田の大神に御縁を結ばれ、今回の人生をスタートした私ですが、昨年は熱田神宮で何度もセミナーを開催させていただきました。会を重なれば重なるほど新な発見があり、自分も多くのことを学ばせていただいてます。そして、もっと深くを知って事をやっていきなさいということでしょうが、さらに深くを知るための資料まで与えられました。与えられたものには、大神や過去で熱田神宮を守っていらっしゃった神職の方々や関係者の方々の想いがいっぱい詰まっていて、魂に響いてきます。
以下、終戦直後の様子が記された部分を抜粋します。
終戦
昭和二十年八月十五日 終戦
混乱と虚脱の中にあって、神宮当局が生命に代えてもやりとげねばならぬ一事があった。終戦と同時に当然上陸を予想される占領軍から、如何にして神宮を護り抜くかという事である。幸いにして占領軍から不当な干渉圧迫がなければよい。だが武力を背景にどの様な事態が起こるかを予想することは不可能であった。
既にこの年の七月初旬、政府首脳の間では伊勢、熱田両神宮を万一の場合に奉遷すべき方途について内々の検討が加えられていた。終戦の日、篠田権宮司が上京していたのは、もし本土が戦場になる場合について内務省との協議の為であった。篠田権宮司は終戦の報を聞くと同時に、内務省、宮内省と能う限りの協議を遂げて、即日帰名の途についた。翌十六日、神宮に帰着した篠田権宮司の報告にもとづき、緊急重大な措置が決定された。
八月二十一日、極秘の中に、長谷宮司が奉仕して、神儀奉遷の儀が行われた。奉遷の目的地は岐阜県水無神社、御料車は東海軍管区司令部から派遣された乗用車二台であった。
奉遷後約一カ月、占領軍も進駐も一段落しその動向も或る程度の見通しをつけることが出来た。九月十九日、再び御動座。篠田権宮司が奉仕して水無神社を後に無事熱田神宮に還座せられたのである。
この事に関しては、これ以上記述を避けたいと思う。宮司権宮司を始め神宮神職、関係者一同の当時の痛恨、恐懼の情は、到底筆の及ぶとことではないと考えられるからである。
ただ、木戸内大臣日記の昭和二十年七月三十一日の条に次の記述があることだけは、謹んで記録にとどめておきたい。
御召ニヨリ、午後一時二十分御前ニ伺候ス、大要左ノ如キ御話アリタリ・・・・・・・・・
伊勢ト熱田ノ神器ハ結局自分ノ身近カニ御移シテ、御守リスルノガ一番ヨイト思フ・・・・・・・・・万一ノ場合ニハ自分ガ御守リシテ、運命ヲ共ニスル外ナイト思フ、謹ミテ拝承云々
同年十二月十五日、連合軍総司令部から神社弾圧を目的とする「神道指令」覚書が出された。当神宮に対する国、県、市など一切の公的団体の如何なる援助も、この指令によってすべて断ち切られた。人心は極度に荒廃し、焼野原と化した熱田神社にとって、この指令は、瀕死の病人の頭上に仮借なく降り下された鉄槌の様な感じさえ抱かしめた。
だが、境内の到る処に瓦礫の山と化した悲惨な焼跡を露呈してはいたが、千古の緑を湛えた熱田の森は依然幽寂の姿をとどめていた。それにもまして、神霊の厳としてまします事実は、如何に世情が変わろうともいささかのゆるぎもなかった。さればこそ、言語を絶する悪条件の中から、早くも復興への槌音が力強く響き始めたのであった。
云うまでもなく、建築資材は皆無に近かった時である。復興の兆しは微かではあった。しかし、幸いにして焼失を免れた西門外の錬成道場(旧宮庁)この建物も六月九日の爆撃による爆風で相当の被害を蒙ってはいたが、応急修理の上この施設を仮宮庁とし、復興への足がかりとして、こうした非常に困難な事情の中に昭和二十年十一月から十二月にかけて、警衛課仮庁舎(十一月二十三日)、上知我麻神社(十二月十五日)、職員職舎(十一月十五日)など、いずれも仮建物ではあったがそれぞれの工事に着手し、戦災と同時に消えていた境内電灯線を開通せしめた(十一月二十四日)。又奉賽業務に事欠いてはとの配慮から設けられた神楽殿も名だけの天幕張りのものであったから早速角南技師等を招いて神楽殿の設計も開始した(十二月三日)。このように復興に寄せるすざましいばかりの意慾は次から次へと力強く果敢実行に移されていった。
昭和二十一年。元旦のみで百万以上の参拝者を見た戦前とは比べ様もないが、それでも正月五日間で四十万人の初詣に接した職員は奮い立った。
仮神饌所竣功(一月一日)、神知我麻神社竣功、遷座(一月四日)、高座結御子神社地鎮祭(四月四日)、警衛課上棟祭(同日)、同竣功祭(八月八日)仮神楽殿起工奉告祭(九月四日)、同新殿祭(十一月七日)。
中には、数少ない焼残りの建物を二棟三棟と集めて、一棟とするといった苦心の建物もあったが、まず緊急なもの、参拝者の要望するものを目標に、出来得る限りの方法をとって、一つ一つの仮建造物の工事が進められていった。
この年二月、官国幣社に関する官制廃止。一般の宗教と同じく、宗教法人成立届けを七月三十日県知事充宛て提出。同十一月十九日「宗教法人熱田神宮」の登記を完了。
同年十二月の職員数と昭和四十一年一月現在の職員数を参考までに対比すると次の様になる。当時の状況を窺う一端ともなろう。
宮司(一)権宮司(二)禰宜一四(宮掌以上二五)衛士六(一九)雇二(六)嘱託二(九)事務雇三(一〇)巫子三(一五)工手(一)工丁一(三)宮丁五(一三)技師〇(一)技手〇(一)事務員〇(五)養成所生徒(一三)
計三九(一二四)
昭和二十二年。食べるものも無く、着るものも無く、日々の朝夕に神前に献る神饌の一部を、境内焼跡の菜園で職員が懸命に栽培するのが日課の一つであった。
だが、とにもかくにも復興の手は一日たりともゆるめられることはなかった。
高座結御子神社仮殿竣功、遷座祭(三月二十七日)、下知我麻神社竣功(四月九日)、鈴之御前社竣功、還座祭(七月二十五日)、総代会に於いて名古屋市田淵復興局長井上建築課長等都市計画問題について懇談(九月一日)、菅原社竣功、還座祭(九月十九日)、大国主社、事代主社竣功、還座祭(十二月十四日)。
この頃、神宮当局へは各方面から相ついで、熱田神宮の諸施設復興の要望、懇請が寄せられていた。中には社殿その他再興の用材を献納する人々も現れて来た。又昭和二十三年に竣功した茶席清雪庵、六友軒などの様に、献茶会という団体を組織して、施設を献納する場合もあった。
遠近、多寡を問わず、復興の一助にと真心からの浄財が寄せられ来た。いよいよ神宮として、復興への本格的な活動を展開すべき機運が熟して来たかの感が強くなっていった
しかし、神宮では、物心共に荒れ果て、日々の糧に苦しむ市民生活が一応の安定を見るまでは、積極的な復興造営活動を控える、という方針をとった。恐らくは、大神の御心も民生の安定向上をこそお望みに違いないと拝察申し上げたからに外ならなかった。日々の奉仕の度毎に、最低限の仮社殿で雨露をお凌ぎいただかねばならぬ申し訳なさに身を切られる想いを重ねながら、ひたすら復興の機の近いことを祈った。
こうして悪夢の様な戦後の二年、三年が過ぎた。そしてやがて本格的な造営への胎動が兆し始めた。
昭和初年以降数次にわたる、造営、拡張、整理は、既に述べた通り、云わば国家の力による主事業を軸として営まれたものであった。だが、来るべき造営の原動力は全く全国崇敬者一人一人が大神へ捧げ奉る真心の結集そのもの以外にはあり得ない。その困難さはもとよりであるが、御鎮座以来千八百年、いっときと雖も曇り給うことのなかった、無辺の神徳を、国民一人一人の胸の奥底まで、照り徹らせる又とない大切な機会でもあったのである。
云わず語らずの裡に、関係者一同は心底深く決意を秘めて、徐々に「熱田神宮造営会」結成への準備が育まれつつもあった。(抜粋終了)